これまでのイベント

教室・講座・講演
講演会「メディアが見た「飛鳥」」
2025年11月30日(日)

搭乗体験
親子で楽しめる
YS-11機内特別公開
2025年12月13日(土)
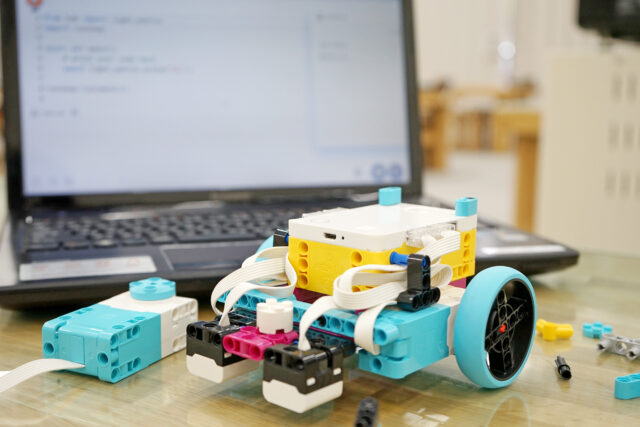
教室・講座・講演
親子で楽しめる
ロボットシステム教室(Python パイソン)
2025年11月16日(日)
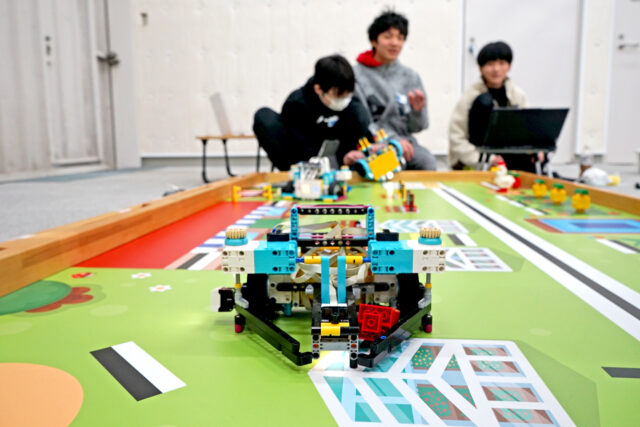
教室・講座・講演
親子で楽しめる
ロボットシステム教室(初心者)
2025年10月4日(土)

教室・講座・講演
親子で楽しめる
エアーロケット製作教室
2025年11月8日(土)
募集終了

教室・講座・講演
親子で楽しめる
作ろう!ゆらゆら飛鳥モビール教室
2025年12月6日(土)
-640x427.jpg)
教室・講座・講演
航空写真家・赤塚聡さんによる写真講座
2025年11月8日(土)
募集終了

教室・講座・講演
アンドリュー先生(紙飛行機作家)のペーパークラフト
2025年11月24日(月・祝日)

教室・講座・講演
親子で楽しめる
紙飛行機教室
2025年10月19日(日)